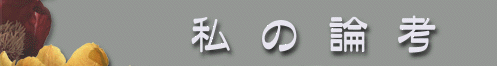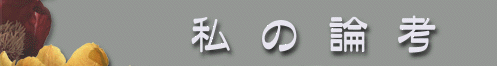市民と法 NO12
個人債務者再生手続の位置づけと実務上の留意点
司法書士 芝 豊
はじめに
個人債務者再生手続(以下個人再生手続という)が平成13年4月施行され、この小論執筆時点で6ケ月が経過した。
この短い期間では、全国レベルでの申立件数の把握も困難で、また私が所属する静岡県司法書士会における申立状況を調査するにしても、サンプル数が少なく分析をしても有意味な結果を求めることは期待できない。またこの法律の構造・内容等については本誌でも既に詳細な解説がなされ、類似の書籍も多数出版されているので、それを参考にしていただきたく言及しない。
そこで本論では、この法律の位置づけ、我々司法書士にとってこの法律が如何なる意味を持つものか等を考察していき、現時点における運用の実際等を論じてみたいと思う。
倒産処理手続の一分類方法
倒産処理手続を大別して、再建更生を目的とするものと、解体清算を目的とするものと把握することは定説といってよい。この分類にしたがえば、前者に属するものに、会社更生法・商法の会社の整理・民事再生法・特定調停法があり、後者に属するものとして破産法・商法の特別清算があり、双方を目的とするものに私的整理がある。
また再建更生を目的とする倒産処理とは、主体を市場に留まったままの状態で処理する手続であり、解体清算型は市場から退場させて行う手続である。もちろん倒産処理手続の適用対象は法人・自然人等すべての法的人格者である。ところで、我々司法書士が扱う倒産処理手続の適用対象は、その大部分が自然人であるといっても過言ではない。もちろん極めて小規模な会社の破産申立を経験したことのある司法書士も多数いることとは思うが、数からいえば圧倒的多数は自然人の倒産処理手続である。
そうであるとすれば、我々司法書士の扱う倒産処理手続は、定説となっている分類方法と違う分類が可能となる。例えば解体清算を目的とするといわれる破産制度である。
確かに破産制度は、債務者の財産状態が悪化し、その総財産をもって総債権者に対する債務を完済することができなくなった場合に、債務者の持つすべての財産を清算して、総債権者に公平な弁済を与えることを目的とする裁判上の手続であり、清算型の典型的なものである。しかしながら自然人の破産の場合は、免責制度が存在することによって、解体、清算ではなく債務者の経済的再建を図るものとしての機能は大きく、その側面に重点をおけば破産制度もまた再建更生を目的とする再建型手続ということもできるのである。そしてまた圧倒的多数を占める同時廃止型破産手続においては、90%以上免責が許可される現状においては、最も強力な再建型手続ということができる。
個人再生手続の存在の周知に伴い、同法の適用を受けようとする相談が増加している。しかし仔細に債務者のおかれている現状を聞き取ると、そのほとんどは支払不能状況であり、破産の適用を受けるのが適当であるという事例が多い。ところが相談者の大多数は「破産だけはしたくない」と頑強に拒否するという場面にしばしば遭遇する。もちろん破産拒否には相談者の側に制度に対する誤解があることは否定できない。曰く、旅行ができない。戸籍に記載される。選挙権がなくなる。子供の将来に影響する。そして人間扱いされない。これらの誤情報の発信元は特定できないが、いずれも虚偽であることは説明すれば相談者も納得する。それでもなお相談者が破産を拒否する理由とは何であろうか。その一因として我々が相談者にする倒産処理手続の説明の仕方にもあると最近私は考えるようになった。相談者から倒産処理手続の概要の説明を求められたときの私の返答は次のようなものであった。「特定調停とは現在の債務額を利息制限法に引き直し再計算し、その債務を原則3年で返済する手続。債務者再生手続とは計算により元本をカットし最低弁済額を決定、その債務を3年ないし5年で返済する手続。破産とは、現在持っているすべての財産を提出する代わりに債務の免除を受けるという清算型の手続です。」この説明で別に間違いはないのであるが、不親切であるという謗りは免れないであろうと考えるようになった。
そこで私は現在では次のような説明をしている。「司法書士が行う手続には3種類があります。いずれも現在のあなたの経済環境を改善させ、生活経済の再建を手伝う手続です。特定調停とは・・・。債務者再生手続とは・・・・。そして破産手続とは・・・。いずれもあなたの現在の経済的苦境を改善し再建を図る制度です。その面では破産も他の制度も何ら変わりありません。」もちろん相談者にこのような説明を試みても、すべて奏功するわけではない。しかし債務者再生手続をとるには、収入が少なすぎ再生計画案の作成ができない債務者、特定調停を申立てるのには債務額が多く債権者の合意が得られそうにない債務者、これら困窮する人々には選択肢はあまり残されていないのである。そうであれば、彼らの救済のためには、破産制度のもつ多面的な効果を理解させることも肝心であり、そのためには我々は自然人の破産は免責制度が整備されているのであるから、再建型手続であるという側面を強調する必要があるのではないだろうか。
司法書士にとっての個人再生手続
新たに創設された法律の評価は、それがどのように市民に適用され、どのような効果を社会全体におよぼしたかという視点でなされるべきもので、それを一職能にとっての法律という形で評価するのは愚の骨頂であることは百も承知であるが、あえて論ずるのは、この法律が司法書士にとっては画期的なものであって、従来の司法書士がおこなう債務整理手続を質量とも拡大深化させるものであるということを、明確に認識しておかなくてはならないと考えるからである。同時にこの法律を司法書士が有用に活用できない場合には、司法書士という職能の存在意義自体を問われることにもなりかねないと危惧するからである。
司法書士が多重債務者の債務整理を職務としておこなうようになって、10年前後の歳月が経過した。もちろんそれ以前にも先駆者が各地においてこの問題について積極的に発言し救済運動に携わってきたことは事実であるが圧倒的に量が少なく、司法書士という職能が、この問題に関与していたとは到底いえない状況であった。(なお、この経過については拙稿「司法書士による被害者救済の歴史と現在」1999年クレサラ白書に詳述)だが、この10年の間で種々の障害もあったが、クレサラ問題として多重債務者の整理は司法書士の職務として定着し、着実に実績も積んできた。
当時の司法書士が債務整理の手段として手にしていたのは、破産の申立と調停のみであった。私的整理は弁護士法72条の問題があり、我々が手がけることはできない分野であり、債務額が大きく、減縮しない限り支払を継続できない場合、将来にわたりある一定程度の収入が見込めるのにも関わらず、債務者の職業が破産による資格制限の対象となっている場合、債務者が不動産を所有している場合、免責不許可事由が存在する場合等、弁護士のおこなう私的整理を選択するのが適当であると思われる事例は知り合いの弁護士を紹介するしか方法は残されていなかった。したがって職能として自然人の債務整理をおこなうといっても、司法書士のおこなう整理は「限定された状況に陥っている債務者」を対象とするものにしかすぎず、その意味では中途半端なものであった。また当時の債務弁済調停は、調停委員の意識・資質にもよるが、現在の債務額そのものを、将来利息をカットさせ分割払いとすることで良しとするレベルのもので、私的整理の代替とするにはほど遠い手続であった。
新しい法の創設には、社会的な要請がある。現今における未曾有な経済的不況が、多数の困窮者を送出し、困窮者と債権者との利害調整が既存の法では充分に機能しなくなったため、新たな法の創設が求められたのであり、しかもその法は、必ずしも法律事務独占を高らかに歌い上げる弁護士職のみを法の担い手としているのではなく、裁判所に提出する書類の作成を職務とする我々司法書士も担い手の一環としているのである。
右の要請を受け、平成12年2月には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」いわゆる特定調停法が施行され、さらには平成13年4月には個人再生手続が施行された。特定調停法は調停委員の権限を強化したこともあり、以前の民事一般調停と相違して、債務者と債権者との取引過程を精査し、且つ利息制限法金利への引き直しをすることが常態としているため、表面の債務額を大きく圧縮することも可能となった。また個人再生手続においては、最低弁済額を極めて機械的に算出し、何ら交渉することなく元本カットにまで踏み込み再生計画案を立案するのであるから、極めて合理的な債務整理方法となっている。したがって、これら2法の創設は我々司法書士をして「限定された状況に陥っている債務者」から「経済状況の悪化に陥っている債務者」の債務整理の担い手にと対象が一般化していることは深く自覚しておくべきである。弁護士が私的整理で、利息制限法に引き直し債務を圧縮あるいは過払いとし、債務者の経済的更生を図る。弁護士が債権者と交渉し利息・損害金の免除さらには元本のカット(実際には債権者側は元本のカットまではなかなか応じない)まで含め交渉し、債務者の困窮を解消する。このような形の処理手続は、我々には法的に許容されておらず、一方相談者のこれら需要は少ないとはいえず、その度に我々は苦慮し前述のように弁護士に事件を頼まざるをえなかった。創設された2法は、司法書士にも裁判所関与という形で同一の結果をもたらす倒産処理手続に参加する機会を与え、少なくても自然人の倒産処理手続において法的整備はほぼ整ったということができる。
そうであるならば、これら法の整備は我々司法書士の社会的有意性を強めたと同時に弁解する余地のない場所に我々を連れてきたということでもある。この場所から逃げたり、この場所を無視したり、あるいはこの場所でたたずんで何らの実績も残せないとしたら社会は我々の存在意義を否定し人は我々に失望するであろう。
個人再生手続と司法書士の関与
個人再生手続が施行され、現時点で6ヶ月が経過している。現時点での極めて素朴な感想は種々の面で簡略化されているのにもかかわらず手続がかなり重いということである。もちろん債権者・債務者及び利害関係人のすべての法律関係を整序し、且つ債権者にとっては債権カットという極めて重大な結果をもたらす手続であるから、慎重で適正な手続が求められるのは当然のことでもある。
意外に思われるかもしれないが、倒産処理手続に共通して、最も重要なことは「書式」と裁判所の「取扱い」である。倒産処理手続は迅速性・緊急性を要し書式がある程度統一されていないと手続開始の時機を失する恐れがあり、また取扱いが統一されていなければ、倒産処理手続の見通し、あるいは法的価値判断に齟齬が生ずる恐れがある。現在までのところ最高裁が申立書および陳述書の統一書式を公開しているので書式に関しては、それほどの混乱を生じていないようであるが、取扱いに関しては地方裁判所によって大きな違いがみられるようである。
また手続の重さは、ある意味では施行されたばかりの法律の宿命でもある。例えば同じ倒産処理手続で同時廃止型破産の申立について20年ほど前は、書式等も統一しておらず、併せて債務者に「報告書」という書面に多重債務に陥った経緯を代理人宛あるいは司法書士宛に申述させ、さらにその報告書を元に申立書を作成し、債権者には意見聴取をおこない、長時間の破産の審尋もあり、破産決定・確定から2週間以内に免責の申立をし、免責の審尋には免責異議を申立る債権者も当初は多く、免責の決定まで最低1年の歳月を要した。現在の破産の申立が、全国ほぼ統一した書式・陳述書を使用し、陳述書の内容が極めて細部にまでおよぶものの合理的な内容となっており、破産の審尋をおこなわない裁判所も多く、期間もまたほぼ6ヶ月と短縮され、全体に使いやすい手続となっている。これは破産手続を簡略化したというよりも、裁判所・申立人側の長い期間をかけての努力の結果、より合理的手続となり洗練されたという評価をすべきものであろう。そうだとするならば、この施行されたばかりの個人再生手続も、試行錯誤を繰り返しながらも、徐々に合理化され、市民に役立つ法律としての地位を確固たるものとする日がやってくるであろう。現在までのところ、この法律に携わる人間、機関すべてが不慣れなため、極めて多くの労力を強いられることとなっているが、法が定着するまでの過渡的なことととらえ、黙々と実績を積むというという態度を堅持することが我々のとる途であると思われる。
最高裁によると法律施行の4月から7月までの個人再生事件の新受付数は全国で2114件(概数)で、内訳は給与等再生が1567件・小規模再生が547件である。この数字が予想外に多いのか、少ないのかは判然としないが、平成12年の破産申立件数が約14万件で1ケ月当たり1万1666件、個人再生の申立件数が1ケ月当たり528件となっている。これら個人再生手続に司法書士が全国的にどれだけ関与しているかは不明であるが、私の地元静岡地裁の本庁においては同期間の申立件数46件のうち36件が司法書士による申立である。司法書士の関与を地裁管内別で考えれば、同管内の司法書士の多重債務者救済の実績と正確に比例するものとなるであろう。個人再生手続も倒産処理手続の一分野であることは論を待たず、倒産法の基本理念の理解および過去の実績に裏付けられた信頼がなければ、市民は相談にさえ訪れないこともまた自明である。また裁判所の司法書士による個人再生手続の関与についての見解も、「弁護士の申立に比して申立書類等の出来が悪いという面は認められない」「弁護士が少ないため、相談を含め司法書士が事件に積極的に関わり、適正におこなわれている」という積極的な評価がある一方 「手続の内容を理解していない。手続の選択が不適切である事例がある」「法律の理解が不十分であり、取り下げや棄却等に終わる比率が高い」「裁判所からの疑問に対する対応について、やや知識不足を感じるときがある」等厳しい評価がされている現実もある。これもまた各地域による司法書士の倒産処理実務経験の多寡の相違に由来していると思われる。
自然人の倒産処理手続の選択は極めて難しく、多方面からの検討を加え且つ債務者の経済環境、家庭環境、職場環境、さらには人間性までも洞察力を持って観察し結論を出さなければならない。特に不動産等財産を所有していない自然人の倒産処理手続は、計算上再生計画案立案が可能であっても、最低でも3年という長期間の返済を計画案どおり続けていくことが債務者の経済的更生にとってベストなのか、履行は可能なのか、アメリカの同種の再生手続の履行が40%にも充たないことから考えれば、社会環境の相違があるとはいえ、日本の再生手続の履行率が極めて高い水準で推移できるとは思われない。そうだとすると債務者の経済環境の更生が遅れるのみではなく、債務者並びにその家族にも不成就という不名誉な心理的痕跡を残す結果となる。もちろん私がここで述べていることはだから破産要件に合致すれば破産を選択しろといっているのではない。ともすれば倒産処理手続の経験の少ない司法書士は、法律ができると、その要件に合致すれば新しい法律の適用を求めるものであるが、倒産処理の選択は、正に薄氷を踏む思いで全能力を傾斜して望まなければならないほど微妙なものがあるということを胸中深く刻み込み対峙して欲しいと願っているからである。
個人再生手続の運用と問題
個人再生手続の最も大きな特徴の一つは、「住宅資金貸付債権に関する特則」の新設であろう。倒産法制の改正作業のなかで「債務者が現に居住している住宅を取得する目的で締結された消費貸借上の債権で、当該住宅を担保とし、かつ、分割払いの約定がされているものについては、担保権の実行により、債務者は居住する住居を明け渡さざるをえず、生活の基盤を失うことになるため、住宅を保持させるという社会政策的見地から特段の配慮が必要である」との意見がだされ、これを受けて新設された規定である。住居を保有している債務者の大部分は、住居を単なる財産的価値として評価するのではなく、それ以上のもの、自分の存在根拠を表象するようなものとしてとらえる傾向があり、したがって住居を手放すことに心理的抵抗は大きく、それを告げたとたん債務整理が進まなくなってしまうことが往々見受けられた。したがって「住居を手放すことなく債務整理ができる」という法の新設は住宅ローンの支払いに呻吟している債務者にとって大きな朗報である。しかしながら実際にシュミレーションをかけてみると特則の適用が困難な場合が少なくない。これは、そもそも住宅ローンの支払いが困難になった理由が、突発的・一時的出費ではなく、リストラによる転職、勤務先経営不振による減給、同ボーナスカット等恒常的な収入減に由来しているからである。もちろん法は、このような事態を想定し「認可決定確定前の延滞部分の弁済方法」(法199条1項)を3年ないし5年と定め、それでも再生計画の遂行が困難な場合は「約定最終弁済期の延長」(同条2項)さらには「元利金弁済の猶予」(同条3項)そして最終的には「権利の変更を受ける者の同意」(同条4項)があれば、その他の変更も可能として法的手当をしている。だが法199条1項に定める原則に従うとすれば、再生債務者は通常の住宅ローンの支払い・再生計画の基づく再生債権者への支払い・さらに延滞部分の支払いとハードルは高く、収入減に起因して住宅ローンのみの支払いさえ困難になった債務者にとっては、特殊な要因(例えば子供等の就職・生活費援助等)が付加されなければ遂行困難であろうと思われる。同法2項および3項はさらに毎回の支払いを減額して遂行可能性を高めているが、現在の社会情勢を鑑みればなおハードルは高いといわざるをえない。結局同条4項の同意型が最も現実的な弁済方法であると思われ、住宅ローン債権者にとっても再生計画による弁済を受ける方が破産手続により弁済を受ける額より大きければ有利であり「同意型」も充分説得力を持つ規定であると思われるが、一方住宅ローン債権は、そのほとんどを保証会社が保証しており、住宅ローン債権者にとっては、同意型によって債権カットに応ずるよりも、破産手続により保証会社から代位弁済を受けるほうが有利な場合が少なくない。このように考えると「住宅資金貸付債権に関する特則」の適用範囲はかなり限定されてしまうというのが現在の実感である。右の実感を裏付けるかのように、平成11年に住宅金融公庫だけでも1万5000件の代位弁済を受けており、この法律の施行により適用を受けようとする人が爆発的に殺到するという予想は現在のところあてはまらない。
さらにまたこの条項の解釈をめぐって実務上の混乱がある。再生債権は特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めによらなければ弁済をしてはならないが(法85条1項)住宅ローンは別除権として約定どおり弁済することは可能か。可能としたならば保証会社が直接担保を取っている場合はどうか。逆に弁済をしてはならないとした場合に、再生手続開始決定から再生手続認可決定までの間の住宅ローンに損害金が賦されることになるが、その損害金は住宅ローン残元本に対して賦されるのか、あるいは弁済期の到来した各弁済期ごとの元本につき賦されるのか、という問題である。この問題は再生計画作成時に大きな相違となる。すなわち開始から認可までの間弁済することができず、かつその間の損害金が残元本全体に対して賦されたとしたと仮定してみれば、例えば住宅ローン残元本2000万円、損害金15%、開始から認可確定までの期間6ヶ月とすれば、損害金は150万円にもおよび再生債務者にとっては過大な負担となる。一方別除権として約定どおりの返済が可能ならば当然損害金は付加されず、また各弁済期ごとの元本に付加される場合にも、全体の元本を対象としたものより、極めて僅少な額の損害金となる。このように取扱い・解釈の相違により結果が大きく相違することは望ましいことではない。最終的な解決は立法に待つしかないのかもしれないが、この特則が住宅ローン債権者に極めて有利な制度であることを踏まえ、他の一般再生債権者の負担を絞量すれば、別除権として弁済可能とするか、あるいは弁済できないとする場合の損害金を付加する元本とは弁済期の到来した分割払い金の元本とすることが、公平の見地からみても妥当であろう。
住宅資金の特則の適用を受けるためには住宅ローン債権者との交渉が不可欠になる。規則にも再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議しなければならない(規則101条1項)と定められている。したがって金融機関側もこの法律の知識が不可欠であるところ、営業店レベルでは、個体差はあるが、一般的には研修を充分受け基本的な知識が備わっているとは到底いえない状況である。銀行等の持つ諸機能が単なる個人との貸借を越えて、極めて公的色彩の強い存在であることを鑑みれば、この特則の立法趣旨を理解し再生しようとする債務者に、できうる限りの協力が必要であるし、それが公的存在としての銀行等の使命であろう。
自然人の個人再生手続の申立の要件が「破産の原因となる事実を生ずるおそれのあるとき」であり、破産原因である「支払不能」までには至らないが、このまま放置すれば客観的にみて近い将来支払不能に陥る蓋然性が高い状態をいうのであるが、経験則からいって消費者金融からの借金は150万円ないし200万円程度の借金から急激に負債総額が増大する。返済資金捻出のために他の消費酒金融から借入をおこし、いわゆる自転車操業が始まるからであるが、この時に適用ができれば支払不能状況に陥るのを阻止できるのであるが、個人再生手続には「最低弁済額」の規定があるため、適用に躊躇する場面がある。最低弁済額100万円、再生委員費用、申立費用、予納金および裁判所への出頭による休業等、かつ信用情報がブラックとなるのであるから、この程度の負債では、この法律を適用するメリットが直截にみえてこない。反面、ある程度の収入があり負債額も多額である場合は有効な債務整理となる可能性がある。基準債権額が1500万円から3000万円以下の場合の最低弁済額は300万円であるので、もちろん清算価値基準を充たす必要はあるが有効な債務整理となるであろう。また以前から活用方法として指摘されていた免責不許可事由が存在する場合の債務整理として破産申立に代わる有効な手続であることは間違いない。(但し免責不許可事由の存在の認定は慎重にされるべきで、裁量的免責、一部配当を条件に免責許可がだされる事例は多数ある。)さらに破産宣告による資格制限のある職業に従事している人にとっても個人再生手続は有効な債務整理となるが、問題もある。例えば「警備業」に従事している警備員は資格制限の対象(警備業法第7条)となる。確かに警備業は現金・貴金属の運送等が主要業務となっているための制限であるが、一方警備業は道路工事現場等の交通整理の仕事も業務としており、そこで働く人々の収入が相対的に低く、経済的な困窮に陥っている人もある。ところが資格制限のため破産の申立ができず、転職するにも昨今の社会情勢から就労先はほとんどなく、個人再生手続を使うには再生案が立案できないと八方塞がりの状況に陥ってしまうことがある。自然人の倒産処理手続による資格制限も従事する仕事の質を細分化し見直す必要もあり、緊急の課題である。
親族の一人が会社あるいは個人で事業を行っている場合、他の親族が保証債務を負担せざるを得ない立場となってしまうことは現実社会ではよくあることである。特に昨今の景気後退による倒産を防ぐため、各地の保証協会の保証を条件として銀行等が「倒産防止資金」として事業家に融資が実行された。ところがそれにも拘わらず、事業家の倒産は増加傾向は止まらない。この場合銀行等は保証協会から代位弁済を受けるのであるが、保証協会はさらに保証人をとっているので、今度は協会が保証人に対して求償することになる。親族の一人の経営失敗が、親族全員総崩れとなるのは納得のできる事項ではない。そこで個人再生手続が有効に適用できる場合がある。保証人が財産も保持せず、かつ収入も少ない場合は、破産申立をするしかないが、例えば保証人がサラリーマンで主な借金は住宅ローンだけというときは、この現実化した保証債務を再生債権として個人再生手続の申立が可能である。そうすれば近代日本の成立時から連綿と続いた「保証人の悲劇」も緩和できるだけの力をこの法律はもっているということになる。右は一例であるが、法律に携わる者すべてが知恵を出し合い、種々の社会事象に対し債務整理の効果的な適用方法を模索する努力が必要となろう。
個人再生手続と民事法律扶助制度
平成12年10月1日より施行された民事法律扶助法は、一定の要件に合致する国民の、裁判所等に提出する書類作成援助者として、司法書士の書類作成実費および報酬の立て替えを認めた。司法書士会内部においては、司法書士の存在の有意性をアピールしていたが、どのような職業も社会的存在として有意義であるからこそ現在まで存続しているのであって、何ら特別なことではない。ところが、この民事法律扶助制度によって対象業務とされたことは正に画期的な事柄であって、司法書士という存在が、無数にある職能の一つではなく、「国民が利用しやすい司法制度の実現に資する」ための業務をおこなう者であるとし、税により報酬等を立替する存在とされたことで、極めて公共的の高い職能であると法が認定したことである。背景には社会的不況に伴う困窮者の増大、法律事務独占をいいながら、すべての法律事象に対し充分には対処できていない弁護士会への不満、そして街の法律家を自認する司法書士会に対する期待等考えられるが、現在までのところ司法書士会は期待に充分に応えているとはいえない状況である。
法律扶助協会の平成13年度の事業として代理援助が2万1000件、書類作成援助が1000件としていたが、代理援助が増大し事業計画の修正を余儀なくされ、当初計画より9000件増やして3万件と修正し併せて8億7700万円の補助金の増額を求めている。一方書類作成援助は平成13年4月から8月までの実績は339件で、年間見込みでも814件と事業計画件数にも充たない。また未だに実績なしの会も多数ある。「全国どこにでもいる法律家」「簡裁の本人訴訟は司法書士が支えている」等のアピールを声高に叫んできた職能に経済的困窮者がアクセスしないという矛盾した現象には我々の存在さえ脅かす陥穽が潜んでいることを深く感受しなければならない。
ほぼ同時期に施行された個人再生手続と民事法律扶助法は、困窮する債務者にとって朗報であるばかりでなく司法書士にとっても重要な法律である。この分野で我々が実績を残せないとしたら・・・、と考えるだけで身震いがする。私としては「Z旗を掲げて」の心境であるが、現在までのところZ旗は遠くに霞んで少数の人にしか見えていないようである。
|